- 万博閉幕から

6月11日から13日、ついに待ちに待った万博参戦の日がやってきた。子どもの頃から、1970年大阪万博の書物や色褪せた映像を飽きもせず眺め、そこに映る人々の笑顔や奇妙な建造物を、まるで失われた楽園のように心の中で何度も反芻してきた。
その記憶の中の万博は、半ば神話のように輝き、手を伸ばしても触れられない場所にあった。では、2025年の万博は果たしてどうなのか――そんな期待と、ほんのわずかな恐れを抱きながら、私は夢洲のゲートをくぐった。

まず、視界に飛び込んできたのは大屋根リングだった。テレビや雑誌で何度も目にしていたはずなのに、実物はまるで異次元から抜け出してきた生き物のように、静かに、しかし圧倒的な存在感でそこにいた。陽光を受けてわずかにきらめき、巨大な輪郭を描くその姿は、空と地面を結びつける壮大な架け橋のようでもあり、都市そのものを抱き込む母の腕のようでもあった。
その下を絶え間なく行き交う人々の流れが、まるで血液のようにリングの生命を循環させている。立ち止まって見上げているだけで、胸の奥の古びた引き出しから、子どもの頃の好奇心が音を立てて開いていくのを感じた。
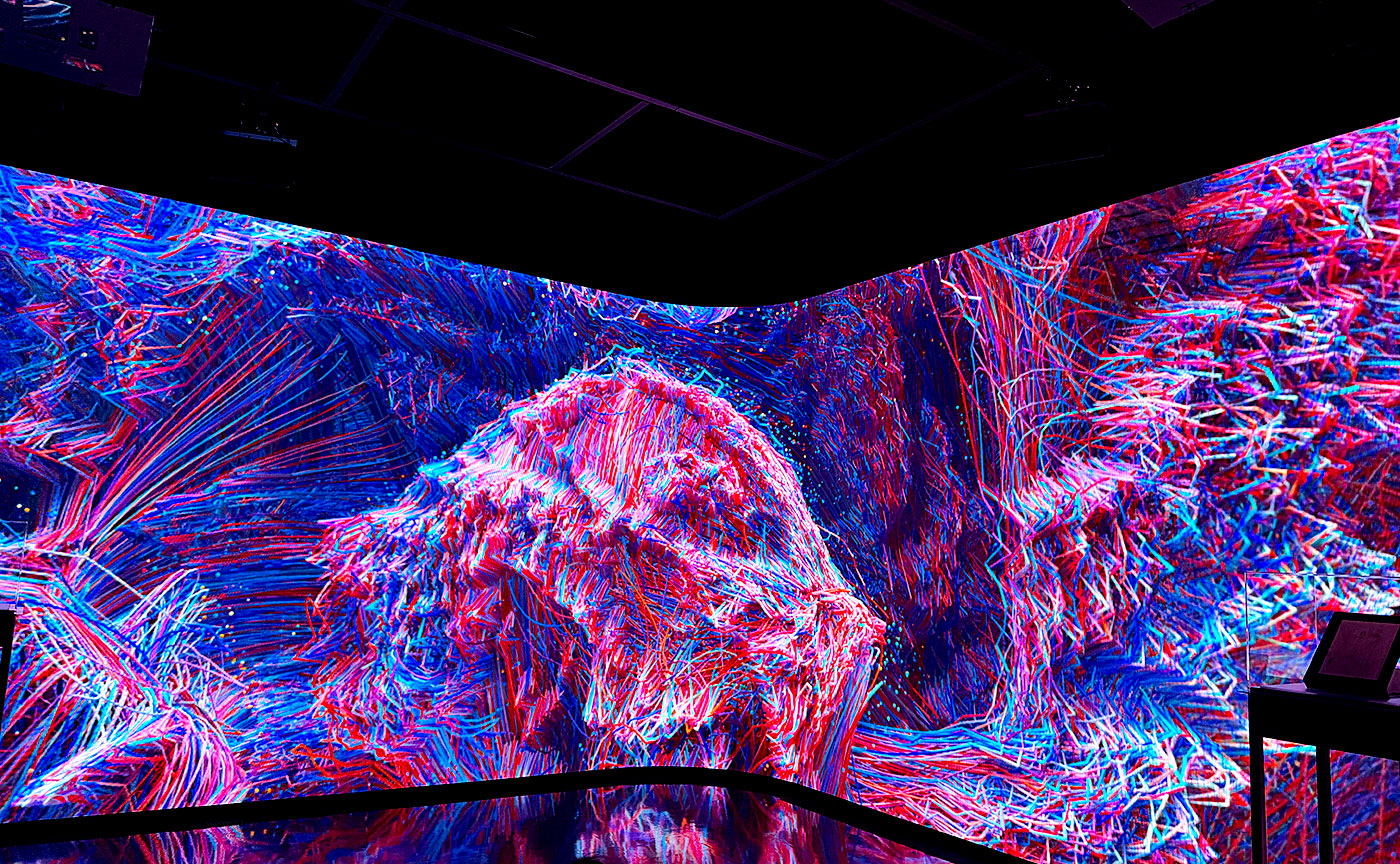
この瞬間だけで、もう満足だと言ってしまってもよかった。だが足は自然と奥へと進み、そこかしこから漂う匂いや音に引き寄せられていく。ネットで事前に知っているはずのパビリオンも、実物の前に立つとまるで別の顔をしている。
巨大な構造物が放つ影、ガラスの反射、遠くから聞こえるざわめき――それらは情報として知っていた事実に、肌触りと重さと温度を与えてくれる。行列に並ぶことさえ、ただの待ち時間ではなく、この祭りの一部となる。知らない人と肩を並べ、少しずつ前へ進むあの感覚は、日常では決して得られない。
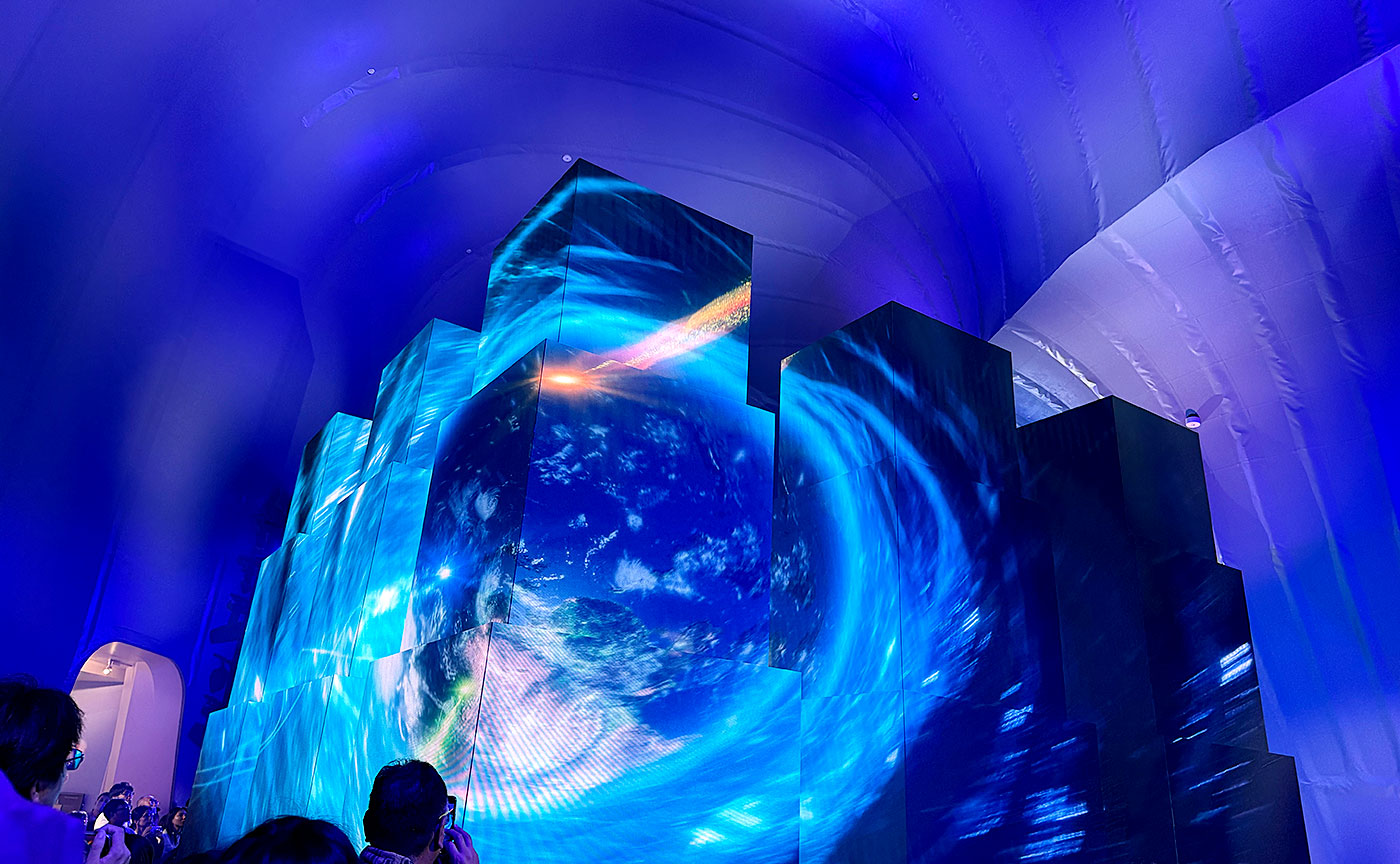
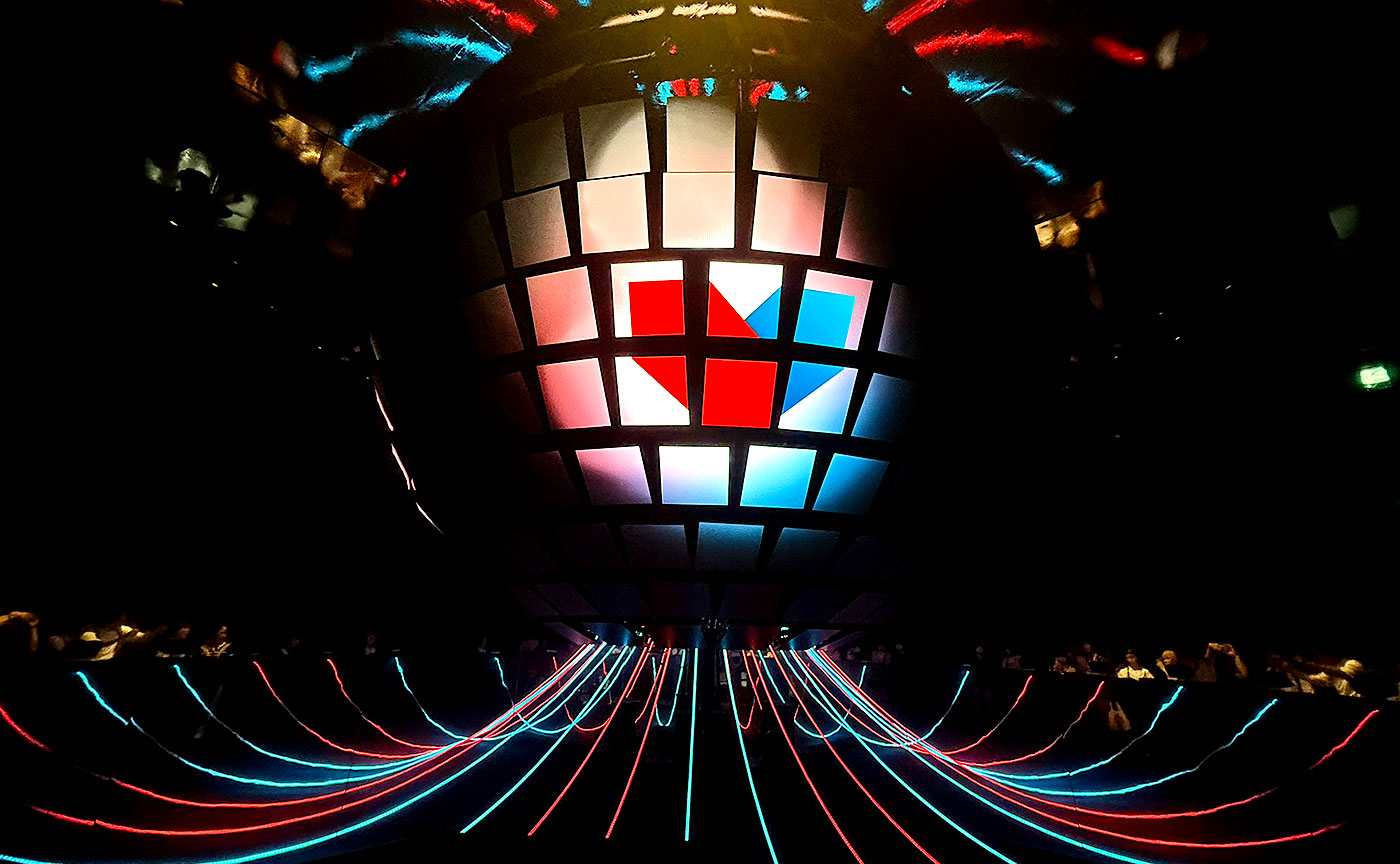
9月には家族全員で再び訪れる予定がすでに決まっていた。しかし、心のどこかで、私は別の計画を立て始めていた。10月、ひとりで静かにこの地を訪れ、誰にも知らせず、再びあの大屋根リングの下に立つ。人混みに紛れ、再びあの呼吸の中へ身を委ねるための、私だけの追撃戦を――胸の奥で、密やかにその決意が灯った。






